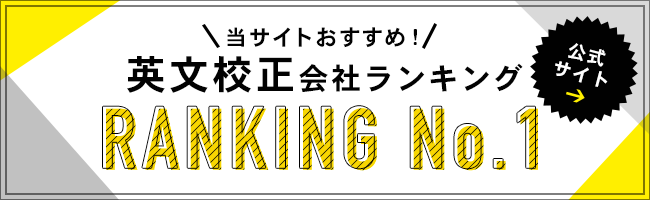英語論文の書き方を分かりやすく解説!

英語論文を書くには、日本語論文とは異なる英語論文の書き方を学ぶことが欠かせません。
それでは、英語論文を書く時に気を付けるべきポイントは何でしょうか。
まず、英語論文は構成をしっかり決めてから書く必要があります。
また、フォーマルな英語を使い、その分野にふさわしい語句や表現を使用します。また、英語論文は簡潔さと整合性も非常に重要で、参考文献の明示は必須です。以下で、1つずつ説明していきます。
コラムの目次
まずは英語論文の構成を考える
英語論文を書き始める際は、いきなり思いついたことを書き始めるのではなく、論文の構成を考え、決めてから書き始めましょう。
論文全体の構成と各パラグラフに書く内容を決めておけば、書いている内にテーマがずれていくことがなくなり、一貫性が保たれ、論文作成もスムーズになります。
英語論文は大きく3つの部分に分けられる
英語論文の種類によって構成は若干異なりますが、どんな論文でも大きく、
- Introduction(序論)
- Body(本論)
- Conclusion(結論)
の3つに分けられます。「序論」ではその論文が何について書かれたものか、一般的な状況はどうなっているのかなどについて説明し、「本論」で論文の内容そのものを、「結論」でまとめを書きます。
また、たとえば学術雑誌に投稿するような英語論文であれば、通常以下の部分も加わります。
- Abstract(要旨)・・・その名のとおり、論文の要約を書きます。
- Method(研究方法)・・・どのような研究方法を用いたのかを書きます。
- Results(結果)・・・実験・調査等の結果を書きます。
- Discussion(考察)・・・「結果」を踏まえて、考察した内容を書きます。
パラグラフごとにトピックがある
上記の「序論」、「本論」、「結論」等は、1つまたは複数の「パラグラフ(段落)」から成り立っています。
英語論文では、基本的に1パラグラフにつき1つの「トピック(話題)」について書きます。
すなわち、各パラグラフは1つのトピックの内容を書き、1つのパラグラフに2つ以上のトピックを含めません。
トピックについて記述した文は「トピックセンテンス」と呼ばれ、たいていパラグラフの1文目か2文目に書きます。
英語論文に合った形式の文章にする
英語論文に使われる語句や表現、文の構造は、話し言葉や友達へのeメールなどに書くカジュアルな文章とは、大きく異なります。
フォーマルな語句や表現を使い、短縮形は使わず、原則として主語に”I”を使わないなどの特徴があります。
フォーマルな語句や表現を使う
同じ意味を持つ語句の中でも、フォーマルな文章でよく使われる語句とカジュアルな場面でよく使われる語句があります。以下で、カジュアルな表現が英語論文ではどのような語句を用いて表されるか、例を挙げます。
「方法」
”way”よりも”method”がよく使われます。
例)The research method adopted in this study
(この研究で採用されたリサーチ法)
「AやBなど」
カジュアルな英文だと”A, B and so on”とよく言いますが、英語論文では、”such as A and B”や”including A and B”などのフォーマルな語句が使われます。
例)Environmental issues such as / including deforestation and air pollution
(森林破壊や大気汚染などの環境問題)
「しかし」
逆説を表す”but”は会話文やカジュアルな文では多用されますが、英語論文では、”however”, “despite this”, “although”の方がよく使われます。
例)However, the result shows …
(しかしながら、結果は…を示している)
「もまた」
英語論文では、”too”よりも”also”や”similarly”などがよく使われます。
例)Similarly, B changed its color.
(同様に、Bも色を変化させました。)
短縮形は使わない
英会話やカジュアルな英文では、短縮形(contraction)が頻繁に使われますが、英語論文などのフォーマルな英文では短縮形は使いません。
× It’s well known that …. → 〇 It is well known that ….
(…はよく知られています)
× It doesn’t show …. → 〇 It does not show ….
(それは…を示しているわけではありません。)
“I”を主語にしない
会話や英語日記などでは自分がしたことや感じたことについての内容が多いので、”I”を主語にした文章がたくさん出てきます。
ところが英語論文では、客観的な記述が求められるため、「一人称」の代名詞である”I”や”We”を主語にするのは望ましくないと言われます。
たとえば、
I predicted that …
(私は…と予想した)
という趣旨のことを言いたい場合、
It was predicted that …
(…と予想された)
のように、主語を「無生物主語(生き物以外の主語)」にして、また「受動態」を用いて書くことが多いです。
ただし、最近は文の構造を簡潔にしてより分かりやすくする観点から、米国などでは”I”や“We”を主語にした論文も見られるようです。
これらの英文スタイルは英語論文の分野や提出先によって異なるため、学術雑誌等に既に掲載されている論文を見るなどして、どちらがスタンダードなのか確認しておきましょう。
英語論文は簡潔に書く
英語論文では、複雑な構造を持つ長い文よりも、意味が明快で分かりやすい簡潔な文の方が好まれます。
また、同じ語句や文の構造を立て続けに何度も使うと、幼稚な文章と見られがちです。
一文を短くする
一文は長すぎないようにしましょう。たとえば、1つの文に接続詞や関係代名詞・関係副詞が2つ以上入っていると、意味をとりづらい文になるだけでなく、英語ネイティブでない日本人が書くと主語と述語の不一致などのミスが起こりやすくなります。
主語・述語関係が分かりやすいよう、短めに書くのが基本です。
似たような語句や文を繰り返さない
英語論文では、キーワードや専門用語以外で、同じ語句や構造の文を繰り返すのは、好ましくありません。
同じ語句が複数続いてしまう場合は類義語に置き換えます。類義語を探すには、英語論文作成には欠かせない「thesaurus(類義語辞典)」を活用しましょう。たとえば、「さらに」を表す”in addition”が続いてしまったら、類義語の”furthermore”や“Also”などもバランスよく使い、同じ言葉を続けないようにしましょう。
また、代名詞を効果的に使うことも、同じ語句の繰り返しを避けるのに役立ちます。
× The length of the object is longer than the length of the other object. →
〇 The length of the object is longer than that of the other one.
(その物体の長さは、もう1つの物体より長い。)
一方、同じような構造の文が続いてしまったら、接続詞を使って2つの文を1つにまとめられないか検討しましょう。ただし、上で書いたように、一文が長すぎたり複雑になりすぎたりしないよう気を付けましょう。
× It shows A. It also shows B. → 〇 It shows A and B.
(それはAとBを示している。)
英語論文では冗長さ(redundancy)を避けることが大事です。代名詞や接続詞を活用して、簡潔な文を目指しましょう。
英語論文は整合性が重要
英語論文では「整合性」が大事です。整合性は英語で、”consistency”あるいは”coherence”と言われ、欧米で英語論文の書き方を学ぶ際に必ず教えられる事項です。
1つのテーマに絞る
英語論文の整合性を保つためには、原則として1つの論文は1つのテーマについて最初から最後まで書き上げます。
つまり、途中まであるテーマについて書き、途中から違うテーマについて書くということはしません。
また、途中でテーマがそれないように、そのテーマに関係のない事柄は、特に必要でない限り英語論文に含めません。
接続詞や副詞等を有効に使う
英語論文の各パラグラフが整合性を持って論理的につながりを持ち、読み手にもその流れが明確に分かるように、接続詞や副詞等を使って各パラグラフのつながりを示します。よく使われる接続詞(句)や副詞(句)の例は以下のとおりです。
接続詞(句): because(なぜならば), although(であるが), and(そして), when(時), as soon as(~とすぐに)
副詞(句):therefore(それゆえ), however(しかしながら), in addition(その上), at the same time(同時に)
接続詞(句)は1つの文の中で句と句をつなぐのに使います。
It is sunny although it is raining.
(雨が降っているが、晴れている。)
一方、副詞(句)は2つの文をつなぐのに使います。
It is raining. However, it is sunny.
(雨が降っている。しかし、晴れている。)
“however”などの副詞(句)は上の例文のように文頭で使われることが多く、副詞句の後にコンマ(,)を置きます。文中で使う場合は、
It is raining. It is, however, sunny.
のように、コンマ2つで副詞(句)を囲みます。
英語論文は参考文献を明示する
英語論文では、必ず参考文献を明示します。もし英語論文で参考文献を記載せずに他の文献から引用したら剽窃(plagiarism)に当たり、厳しい処罰の対象になります。
このため、欧米で英語論文の書き方を学ぶ際は、最重要事項として参考文献の記載の仕方を教わります。
論文を作成するために参考にした文献は、すべて記録を取っておきましょう。
参考文献の記載方法を確認
当記事では一般的なルールをご説明しますが、英語論文の書き方には主にAPAスタイルやMLAスタイルなどがあり、参考文献の書き方にも若干の違いがあるため、英語論文の提出先にどのスタイルを採用すべきか確認しましょう。
通常「文献名、著者、出版年月」は必須記載事項です。
直接引用の場合の書き方
ある文献を参考にしただけでなく、その文献中にある文言を一字一句そのまま書く「直接引用(direct quotation)」をした場合は、その文言をダブルクオテーションマーク(“”)で囲み、その文言が記載されているページ番号も記載する必要があります。
引用部分の文字を斜体にするよう指定される場合もあります。
まとめ
英語論文の書き方には様々な「お作法」があるため、書き方を学ぶことは重要です。欧米の英語ネイティブの学生でも、大学に入学したら論文の書き方を学ぶくらいです。英語論文を作成する際には、最低限上記のポイントを抑えた上で書き始めましょう。
ただ、英語ネイティブでない日本人研究者にとって、国際舞台で英語ネイティブの書いた英語論文と競い合うのは大変厳しい戦いです。論文の内容自体が素晴らしいにもかかわらず、英語という語学の面で論文が不採用になってしまうとしたら大変残念です。
そこで、英語論文の書き方に従って仕上げた論文を、プロの英文校正会社に依頼して校正してもらい、国際的な出版基準を満たす英語論文に仕上げましょう。英文校正会社を選ぶ際は、こちらの比較サイトが便利です。ぜひご活用ください。